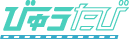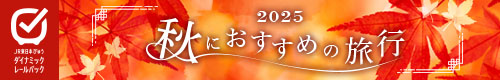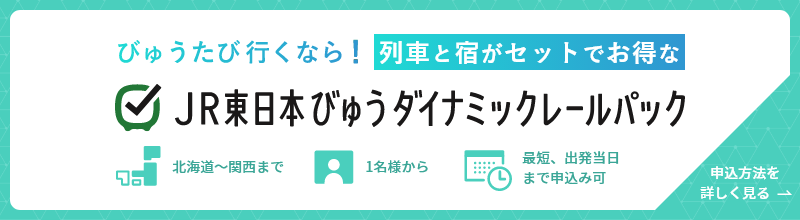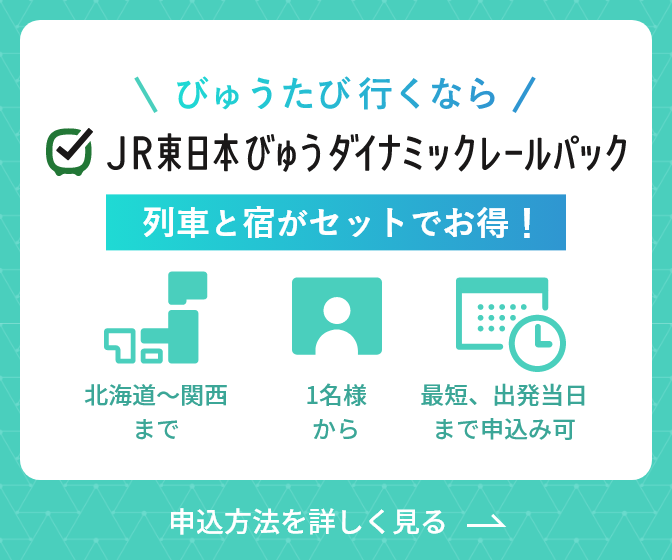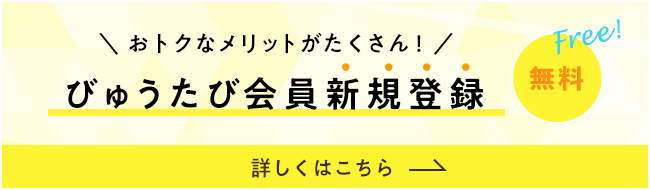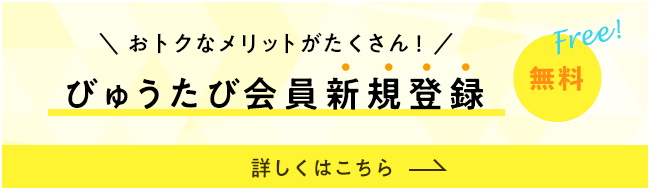自らの手で九谷焼の絵付けにチャレンジし、工芸作家のエネルギーに触れた、金沢の旅1日目が終わりました。
2日目の今日は、九谷焼作家として60年のキャリアをもつ赤地健さんと、定期的に工芸作家の展示会を開催している陶芸家の吉岡正義さんのギャラリーに行って、作品に触れてみたいと思います!
2日目:工芸作家を訪ねる ー 赤地健陶展@As baku B/工房「陶庵」

「金沢21世紀工芸祭」の一環で、さまざまなギャラリーや工房が参加して作品を展示するイベント「金沢アートスペースリンク」。旅の2日目は、そこに参加しているギャラリーを訪れることに。向かったのは、ひがし茶屋街から歩いて10分ほどの尾張町にある赤地健陶展@As baku Bと、少し街から離れた入江町の工房「陶庵」です。
いったい、どんなお話が伺えるのでしょうか。



金沢の工芸に出会いたければ、ひがし茶屋街へ。九谷焼や輪島塗、加賀友禅、金箔などのお土産物屋さんを始め、九谷焼の食器でお料理を出してくれるカフェや料亭などが多く、また「金澤しつらえ」のような伝統工芸品を常時展示しているところもあって、簡単にまとめて金沢の工芸に触れることができます。また街並も、過去へタイムスリップしたかのように美しい日本家屋が立ち並び、日本人も外国人も、和の情緒を存分に感じることができるのではないでしょうか。
さて、そこから歩いて10分、As Baku Bというギャラリーで開催中の赤地健陶展へ到着。
「赤と緑 ー 16歳から表現への挑戦を続けてきた」
〜赤地健陶展を訪ねる〜


16歳の時から焼き物を始め、陶芸の世界で60年以上活躍して、今も現役で作品を手がける赤地先生より、作品への思いや金沢の工芸についてのお話を伺いながら、一点一点、作品を一緒に見せていただきました。
先生の作品の多くには、赤色と緑色が使われています。
「赤一本だけで表現するというのを、40年近く続けているけどね、昔は受け入れてもらうのが難しかった。でも、今は自分らしい表現になっていると思う」
伝統工芸を崩すことが受け入れられなかった時代に、赤一本で表現を始め、反対の色の緑は使う。相反するふたつの色だからこそ色が引き立ち、陶器に表現が出るのだそうです。
驚くことに、絵付けも必ずろくろの上で回転させながらされているようです。
「簡単にいくときもあれば、何度も消してやり直しをするときもあるけどね。でもそれでいい」

「表現に遊び心を忘れないのが自分らしさ」
ろくろの上で生地を作っているとき、さまざまなアイデアが浮かんで、当初の仕上がりのイメージからどんどん変わることもあるそう。
「ろくろでできた太鼓型の生地をね、思い切って縦に切って、開いて、舟のような皿にすることもあります」
よく見ると、赤と緑の絵が入った舟型のお皿は、もともと太鼓型の器だったのだとわかります。

赤の小紋と緑で絵付けされた大皿は、表面が段々なっていて、縁に飾りがついて、お皿自体がくねっと歪んでいます。これは「緑花詰鳥文耳付鉢」という耳付きシリーズ。絵付けは伝統的な小紋で、動きを出すために、線の粗さや細さを変えて描く。すると、全体的に曲がってきて、面白くなったのだとか。
「どの作品もね、面白くならないかなって思って、生地が柔らかいときに、切ったり、歪めたり、段々にしたり、縁に耳をつけたりして遊んでいます」
少年のようなイタズラな瞳で微笑む先生。
いまだに、どう表現したら自分らしくなるか、遊び心をもって考えるのだそうです。
とにかく先生の作品は、普通と違う動きを出すことにこだわりがあるのです。

「日常で使ってもらえる食器づくりを目指す」
蓋物も長く続けてきた作品。先生がすべての作品の中で気に入っているものを伺うと、
「いいか悪いかはわからないけれど、蓋物は30年近く続けてきて、いろいろな方法でやってきたけれど、まだまだ展開していきたいというこだわりがある」と、蓋物作品への計り知れない熱意を感じました。

「それからね、作品は置くより使ってほしい。だから日常で使える食器も作っていきたい」
作品を眺めていると、ひとつひとつ芸術的なオブジェのよう。でも、最大の願いは、“使ってもらうこと”。


食器は40年近くやっているので、作品づくりから切り離せないそうです。
オブジェも小皿も先生にとっては同じで、どちらも常に面白いものができないかと考えるので、日常で使ってもらう食器としては少し使いにくいのではないかと思うそうですが、しかし「何か自分らしい表現をしたい」というこだわりが勝ってしまう。
「普通に使えるものに見えるけれど、ひとつひとつに遊び心を持っているので、同じように見えて大きさや絵付けが違う。となると、日常使いに何枚か買ってもらうのが、少し難しいね」

「金沢の伝統とは、つながっていたほうがいい」
若手の九谷焼作家はパステルカラーを使って作ったり、時流に合わせたデザインにしたり、伝統の九谷を逸脱していることもあるけれど、先生の作品づくりには常に伝統的な柄や色のベースが頭の片隅にあるのだそうで、たとえば小紋など昔からある柄を使って、中間色などは使わずに九谷五彩だけを使って制作している。
「お土産や観光のために作るのではなくて、専門店や鑑賞もできる常設展があって、そこへ市民が普通に来て買って、金沢伝統の工芸を家で使う。それが最高の状態」だと、先生は言います。
作品を日常に使ってほしいという先生の思いから、4枚の小皿を買って帰りました。小紋をベースとしてアレンジした作品で、自然の雲や波などを表現したそうです。
日常に工芸品を――作家の思いを受け、これからは、私もそうしていきたいと思いました。
「自分らしい表現は、旅の出会いのようなもの」
〜工房「陶庵」を訪ねる〜

尾張町のギャラリーAs Baku Bのあとは、入江町にある工房「陶庵」へ向かいました。
工房は、静かな住宅地にひっそりとたたずむ一軒家。オーナーは工芸作家の吉岡正義さんで、2階のギャラリーには彼の作品と、彼が声をかけたさまざまな作家の作品が定期的に展示されています。
吉岡さんが手がける作品には、九谷焼作家が使っている花坂陶石という石を砕いたものなども使われ、色は主に赤と白。
吉岡さんの作り出す赤色は、情熱的な燃える赤だけど、なぜだかほっと落ち着く赤なのです。心地のよい赤で、これは九谷焼で使う赤とは違い、セレニウムや金を使って発色させているそうです。
また作品には「ここだ」というところで、大胆にすっぽりとくり抜いて穴をつくり、太陽と月、陰陽などの“対比”を表現するのだそうです。
「穴を開ける箇所を迷ったりしませんか?」と伺うと、
「出会いなんですよね。ここだ!というところに導かれるんです。それって、小林さんが旅をされている時に、どこかに導かれて、自然とステキな出会いがあるのと同じですよ」と答えてくださいました。



「定期的に開催する個展で、金沢から世界へ、世界から金沢へ」
工房の2階では、他の作家の個展や作家同士のコラボレーション展などが定期的に開催されています。吉岡さんは、日本の作家だけでなく、海外の作家にも積極的に声をかけているとのこと。
たとえば、長い付き合いの韓国の作家とは、毎年金沢と韓国で交互にイベントを開催して交流しているそうです。まさに、金沢から世界へ、世界から金沢へ。
「工芸を通して、日韓の友好を深めることができる」
とおっしゃる吉岡さんの言葉には、工芸を超えた新しい工芸のカタチを感じることができます。

「金沢に生まれてよかった!」— 現役作家が断言する金沢の魅力
金沢では、家族がお茶の先生や三味線やお琴をしていたという方が多く、それは決して珍しいことではないのだそうです。
江戸時代に加賀藩前田家が工芸を愛し、九谷焼を作ったり、輪島塗を使ったり、工芸作家を育てたという歴史があって、昔からずっと日常に工芸が根付いてきたのです。
金沢では、陶芸や輪島塗、加賀友禅などを教える県立高校があったり、作家デビューしてからも作品を発表する場がたくさんあって、そこでお客さんの手に届くという機会に恵まれているのだそうです。
「金沢に生まれてよかった。他の場所だと、陶芸に出会ってなかったと思いますよ。金沢市は工芸家をサポートする環境があって、市役所や県庁がアート関連の窓口となってくれているんです」
今後も、このギャラリーで、いろいろな展示を続けていかれるそうです。
今年1月には、シンガポールで陶芸を始めた陶芸作家の今野朋子氏、イー・ヒースン氏(ソウル出身)、キム・サンキ氏(イチョン出身)と吉岡さんの4人で、それぞれの作品をどういう背景で作ったのかをひもとき、4人の作家の共通点を見つけ出して展示する予定だそうです。
「金沢21世紀工芸祭」をメインに金沢の街と市民の中に根付く工芸のカタチに触れる旅をして、今だけでなく、過去から未来へと続く工芸の価値を感じることができました。芸術的なオブジェとしてだけではなく、日常で使って愛でることで、作り手と使い手が心を通わせる瞬間に価値が生まれる。そのシンプルな関係性をもっと現実に根付かせるために、工芸都市金沢の挑戦は続くのだろうと思います。金沢から世界へ、世界から金沢へ、工芸と工芸を超えた価値の交流や対流の発着地となっていくであろう金沢の今後がとても楽しみです。
今回の旅の行程
【1日目】東京駅→金沢駅→ノエチカ
【2日目】ひがし茶屋街→尾張町「As Baku B」→入江町「陶庵」